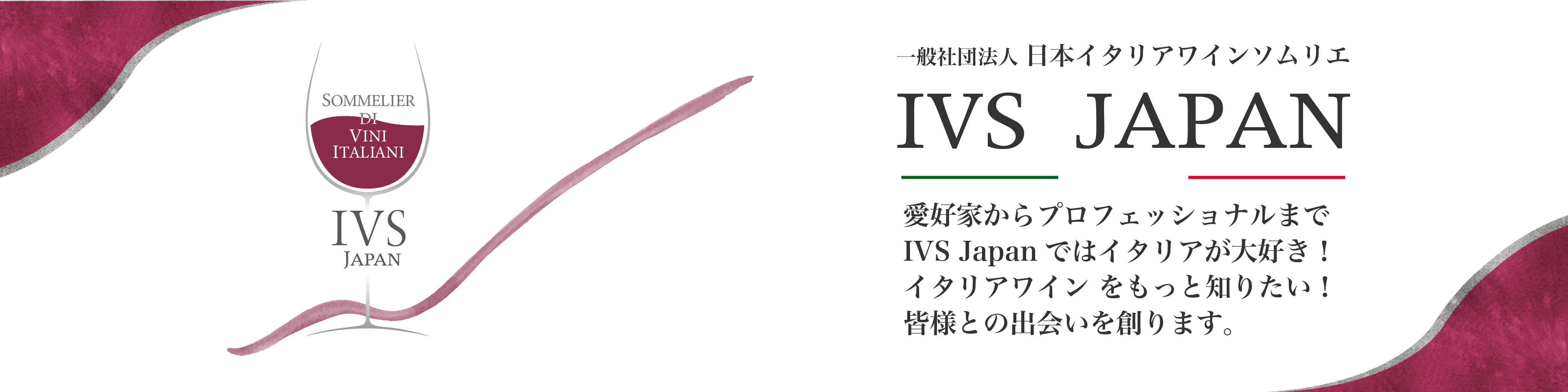西村先生よりご紹介~秋場美恵子/『文流サローネ』 No.79(2016年3月5日)
今年2016年は日本とイタリアの間で始めて修好通商条約が結ばれてから150周年になります。イタリアから最初に日本を訪れたのはキリスト教の宣教師達でしたが、両国の間に正式な条約が結ばれたのは江戸幕府が瓦解する直前の1866年のことでした。イタリアもその5年前の1861年に念願の統一を果たしたばかりでしたが、欧州の蚕の病により崩壊寸前に陥った北伊の絹糸産業を救うため日本から良質の蚕種を入手することが早急に必要とされていたのです。
こうした事情からイタリア政府は日本および中国との間に修好通商条約を結び、併せて現地の実情を文化社会から自然科学にいたるまで広く調査するために一隻の軍艦「マジェンタ号」の派遣を決定します。そしてその指揮を任されたのが海軍中佐のヴィットリオ・アルミニョン(Vittorio Francesco Arminjon, 1830-1897)でした。
アルミニョンは当時35才、イタリア王家発祥の地サヴォイア(現仏領)の出身でジェノヴァ王立官軍学校を卒業、故郷サヴォイアが伊仏間の条約でフランス領となるに従い仏海軍に所属しますが、イタリア王国成立と共に伊海軍に復帰、フリゲート艦、戦艦艦長、海軍砲術学校長を務め、砲術の優れた著作もあり数ヶ国語に堪能で人格も認められたイタリア海軍きっての秀才でした。当時の外務大臣ラ・マルモラと海軍長官アンジョレッティはそんなアルミニョンに白羽の矢をたて、万国の人民を尊ぶ新生「イタリア」の旗を世界に初めて掲げるに恥じぬ自由と独立と無私の精神を持って極東での修好通商条約を締結してくるよう激励、併せて自然科学の研究成果を目指す大航海を命じます。こうしてアルミニョンは艦長(兼)全権という前例のない大任を受け、著名な自然科学、動物学者のデ・フィリッピ、ジッリオーリ両教授を伴い1865年11月8日ナポリからまず南米のモンテヴィデオ(ウルグアイ)に向い、そこから翌年2月2日にマジェンタ号乗組員345名とともに登用を目指して出航します。
地理・貴校及び風雲はらむ日本の政情を熟考の上、一路バタヴィア(ジャワ)、シンガポール、サイゴンを経由して遂に下田沖に到ったアルミニョンとマジェンタ号が「水平線上の雲の上にそびえる荘厳なFuji-yama」を目にしたのは1866年7月4日のことでした。それから幕府と約一ヶ月半の交渉を経て8月25日に日伊修好通商条約を調印、11月には中国とも条約締結、通算2年をかけ世界一周を果たした後1868年の春ナポリ港に帰還します。そして翌1869年には条約の交渉過程と日本事情をまとめた労作「日本及びマジェンタ号の航海記」”Il Giappone il viaggio della corvetta Magenta nel 1866.” Genova. Co’ Tipi del R.I. dei Sordo-muti, 1869[1]がジェノヴァ王立聾唖学院から出版され、歴史的価値ある優れた著作として地理学協会から金メダルを授与されます。アルミニョンは生涯それを大変誇りにしていたと言われます。
さて肝心の日本との条約ですが、まずアルミニョンはナポリ出航前に日本初となる幕府の横須賀製鉄所建設交渉でパリ滞在中だった外国奉行・柴田日向守剛中を訪ね挨拶しています。そして絹糸産業の危機的状況からイタリアが日本の助力を必要としていることを虚心に明かし、純粋に友好と通商を求めて来航予定でいる旨を説明するのです。更に「日本を西洋に紹介したのは一人のイタリア人であった」とマルコ・ポーロから説き、両国の共通点も挙げて日本の美術品には感嘆したと語るアルミニョンの偏見のない態度は細謹な柴田にも好印象を与え、一年後に日本で修好通商条約を締結する2人は出会った初日から一時間も話しこむ程意気投合できたのでした。「柴田と面識のなかった私であるが、今や私は彼の友人(Suo amico)である」きっぱりと述べるアルミニョンからは当時圧倒的な武力を背景に高圧的な態度で日本に臨んでいた列強の公使達とは全く異なる人間性が感じられます。更に彼は海軍図書館から借り出したり自費で集めた日本に関する文献を長い航海中に読破、日本の歴史や文化をしっかりと学んだ上でパリ以来友と頼む幕府側代表の柴田日向守と念願の再会を果たすことになります。「私は友情こめて柴田と握手を交わし、再会できた事を喜ぶとともにパリで論じたと同じ問題について再び話し合うことができるのを満足に思う」と述べた。
イタリア海軍の軍服のアルミニョンと和装の柴田日向守の江戸再会には心温まるものがありますが、幕府側では基本的には新たな条約締結謝絶の方針であり、折しも母国イタリア・オーストリア間の戦争開始が報じられる中、アルミニョンは密かにマジェンタ号の安全と交渉の行方を憂慮します。しかし「数年前に統一なった意太利國[2]は欧羅巴でも屈指の文武の誉れ高いお国柄、仏との関係もあり即今条約を結んでも日本の損にはならぬ故御英断を」彼と会い実際に交渉に当たっていた柴田他7名の外国奉行達が評議の上揃って声をあげます。同盟国フランスと強調しつつも人種や国籍に拘らず相手を尊重し常に友好的な姿勢で交渉に臨んだ全権アルミニョンの誠意あふれる人間性が外国奉行達を動かしたのでした。
こうして遂に8月25日江戸大中寺にて幕府側代表柴田日向守、朝比奈甲斐守、牛込忠左衛門(目付)、伊全権アルミニョンの間で日伊修好通商条約が和やかな雰囲気の中で調印されます。奇しくも14代将軍家茂が亡くなる4日前のことでした。「貴殿はわが国の置かれている困難な状況を良く認識せられ、われわれの譲与しうる以上のことを要求されなかった。我々はこのことに深く感謝している。貴殿の誠意ある態度は今後両国間には常に協調関係がありうることを我等に確約するものである。」調印後そう繰り返した柴田達の言葉を2年後ジェノヴァに帰還したアルミニョンは控えめな矜持をこめて書きしるしています「この言葉は私の胸(animo)を深く感動させた。私はこの言葉を信じたし、今もそれが心からのものであると信じている。日本人の心はフランシスコ・ザビエルの当時と少しも変ってはいない。」アルミニョンが柴田達と交わした信頼と友情はその後多くの人々に受け継がれ、第二次世界大戦中に両国がファシズムに陥るという歴史の荒波をも越え、今150年の日伊文化交流の花を豊かに咲かせるに到っています。