西村 暢夫
古代ギリシア・ローマの食文化の三大要素はパンとワインとオリーブ油だとされています。パンとオリーブ油は人間にとっての基本的栄養素であり、すんなり理解できたのですが、ワインが入っていることに少し違和感がありました。ワインは酒の一種で、食べ物ではないというとらえ方をしていたからだと思います。
ところがイタリア人のワインの飲み方に注目しますと、食べ物を口に入れ、噛んで、飲み込むと、次にワインを飲み、また食べ物を口に入れるというように、食べ物とワインが一体化しているのです。ワインと食べ物はお腹の中でアマルガムになるのです。
ルネサンス時代の大知識人であるプラーティナが著わした「真の喜びと健康について」という本の中に「ワインについて」という項があります。書き出しは「ワインのない夕食にしても、昼食にしても、そういう食事は楽しくないばかりか健康によくない」という文章から始まっています。
ワインを食事の基本的な一要素として重要視する思想は、ルネサンス時代に始まったことではありません。パンとワイン、それにオリーブ油が食の三大要素とされた古代ギリシア・ローマの食文化からずっと続いているのです。
古代ギリシアやローマの人々は、ワインをただのアルコール飲料とは考えず、声明を維持する、健康に欠かせない飲料ととらえていたのです。だからこそ、キリスト教では、ワインをキリストの血の象徴ととらえ、パンをキリストの肉体として尊重したのだと思います。
西暦11世紀末に南イタリアのサレルノにあったヨーロッパ最古の医学校で変種された「サレルノ養生訓」(佐々木巌訳、解説。柴田書店、2001年)にはワインについての話がいくつも出てきます。
第11話に「ワインの効用、その1」が入っています。そこに「よいワインを飲むと、それだけよい体液が生まれる」という記述があります。イタリアの古い話に「よいワインはよい血を作る」というのがあるように、品質のよいワインは最良の体液を生むと考えられていたのです。
第15話の「ワインの効用、その2」には「水だけ飲むことを日課にしている人もいますが、そういう人には黙ってひとりで飲ませておきましょう。水や少量のビールが健康の敵で、よい消化を妨げるのは、疑問をはさむ余地もない事ですからね」と消化には水よりワインがよいのだと述べています。
また消化の問題については、第14話に「ワインを加えれば、羊肉がよい食物にも。薬にもなるように、ワイン抜きの豚肉はあまりよい食べ物とはいえません」というのがあります。訳者の佐々木巌先生は豚肉や羊肉は脂っこいので、ワインを飲みながらでないと消化不良を起すことがあることを、サレルノ医学校の医者たちは知っていたのだと解説しておられます。
この「サレルノ養生訓」の日本語版は佐々木巌先生が英語版(1607年、ハリントン版)から翻訳されたものですが、2001年に柴田書店から出版されて以来、すでに絶版になっていて入手は大変困難になっていました。
そこで「新サレルノ養生訓」を出版したいという佐々木巌先生の希望を元に、ラテン語の原典を参照しつつ、イタリア語版からの翻訳を、翻訳家の森田朋子さんにお願いし、新しい解説を佐々木巌先生にして頂くことにし、目下作業が進行しております。出版元は(株)文流です。
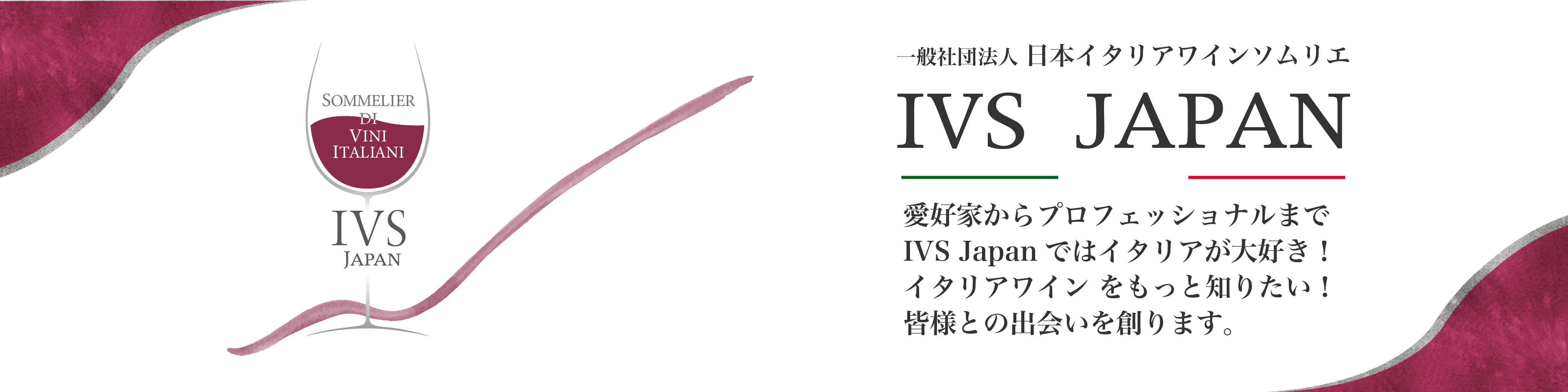
コメント